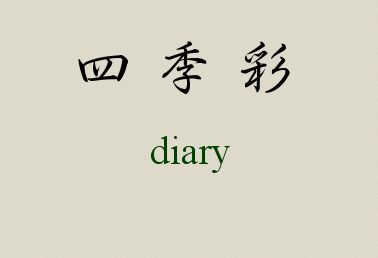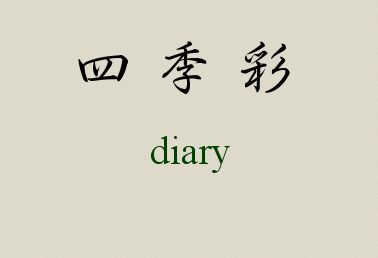見沼くらしっく館で初午の行事食「しみづかり」作りが公開され振舞われました。さいたま市見沼区片柳でのしみづかりは大根と炒大豆を煮込み醤油で味付けした「あっさり味しみづかり」でどなたにも好まれるしみづかりでした。見沼くらしっく館のしみづかりの作り方
大根を鬼下ろしで粗くおろし、節分の残し炒大豆を半割したものを、鉄鍋で30分煮込みました。半割大豆が軟らかくなったら醤油で味付けして出来上がりです。
材料・ダイコン3本(40食分)、半割炒りダイズ300g、醤油適量。
出来たしみづかりは赤飯と共にわらづとに入れ、お稲荷様、荒神様、恵比須大黒、仏さま、神棚、歳神様、井戸神様に供えました。
○わらづと(藁苞)の作り方
稲ワラをひとつかみ(100g)位を中程より下目を結わえ、穂先を表側にしながら上に持ち上げ、ほぐれないようにワラで結います。わらづとは2本一組となりますので、わらづと同士の穂先を結びます。2本一組のわらづとに赤飯としみづかりをそれぞれ入れます。
○しみづかりの呼び名
栃木県を中心に北関東一帯に伝わる稲荷信仰の郷土料理で、古くは平安期頃から食されていると言われています。
読み名、作り方、材料もいろいろで、隣同士の家でも違うといいます。
すみつかれ、すみつかり、すみづかり、すむっかり、すむづかり、しもつかれ、しもつかれい、しみつかり、しみつかれ、しもずかり、つむじかり等です。
○下野地方の「しもつかれ」の作り方
材料はダイコン、ニンジン、炒大豆、塩鮭頭、油揚げ、酒粕です。
好みで昆布、鮭肉、酢、醤油、味噌、塩、砂糖等を使う家もあります。
○しみづかりでいちばん大切なことは、自分で作って食べてみることです。
(さいたま市見沼区片柳・見沼くらしっく館)